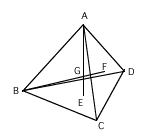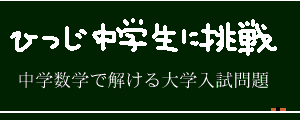 |
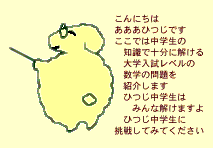 |
ここにある問題は数学と言うよりクイズやパズルのような問題がほとんどです。
ほとんどの問題は小学生でも解けるはずです。中学校の知識が必要なものは*がついています。
| 問題1.教科書* 問題2.東京大学 問題3.日本工業大学* 問題4.日本大学医学部 問題5.全米数学オリンピック問題6.東京大学 |
問題7.東京工業大学* 問題8.京都大学* 問題9. 京都大学 問題10. 一橋大学 問題11. 九州大学 問題12. 自治医科大学 |
問題13.日本大学医学部 問題14.早稲田大学* 問題15.京都大学 問題16.京都大学 問題17京都大学* 問題18京都大学 |
|
問題18 1,2,3,4,5の5個の数を一列に並べる。1番目と2番目と3番目の数の和が、3番目と4番目と5番目の数の和と等しくなる確率を求めよ。 |
2010年京都大学理系の問題。並べ替えは120通りしかありませんから、すべて書き上げてしまえば小学生でも解けそうです。
<答>並んだ数をA,B,C,D,Eと書く。A+B+C=C+D+Eだから、A+B=D+E。5個の数の総和は15だから、Cは奇数でなくてはならない。Cが奇数になる確率は、3/5。さて、C=1、3、5のとき、残りの数のうち、左右の和が等しくなるように、2と組み合わさる数は残り3個のうち一つしかないので、等しくなる確率は1/3。よって、求める確率は3/5かける1/3で1/5。